イギリスの大学院(UCL IOE)で、開発学の修士号を取得!(崎元大志さん)

通っていたUCLの校舎前で
■IOEでの1年間、そして授業はどのようなものか?
–道のりは長かったですが、やっと大学院生活ですね!
長かったですね(笑)。マンチェスターでも色々ありましたが、やはり僕は、イギリス生活の中で、IOEでの1年が一番おもしろかったです。
–IOEではどのような事を勉強されていたのですか?

ロンドンでよく見られる兵隊の行進の様子
僕が取っていたコースは「Education and International Development(教育と開発)」と呼ばれるものでした。
よく、「Development education(開発教育)」と同じだと混同する人がいて、僕も留学前はそうだったのですが、これは全く違うコースなので、気をつけてください。これだと、途上国での開発ではなく、先進国で国際協力を普及していく活動になってしまいますので。
–それ間違ったらシャレにならないですね(汗)。IOEでの授業や卒業のシステムはどのようなものだったのですか?
9月から始まって、2つのタームに分かれていて
・秋ターム(10週間):2コマ授業
・春ターム(10週間):2コマ授業
・フィールドワーク
・論文提出
という流れで、論文が通れば卒業でした。
–1年間でにたった4コマしかないのですか!?
はい、僕のコースは他のコースより圧倒的に授業数がすごく少なくて、週に2コマで合計3時間でした。でも、1つの科目がかなり重たかったです。
–重たいとは?

ロンドン大学(IOE)の構内
1つの授業のために、めちゃくちゃ課題が出るんですよ。毎回「次の週までにこれ読んできてね。」という感じの記事リストがあって。
それが平気で120ページ以上した事もありました。授業にもよるのですが、授業の前日にクラスメイト5人くらいで集まって、読んだ物の意見交換などをする事もあるんです。ですので、準備だけでも相当の時間が必要でした。
–しかも、それは全て英語ですよね。重そうですね。。
はい、そして、1月には論文の準備も始める必要がありました。ですので、本当に図書館にこもって「読んだり、書いたり」などずっと勉強していました。
しゃべる力よりも読み書きの力が相当上がったと思います。
–なるほど、入学前に語学力審査がある理由が腑に落ちました。クラスメイトは留学生が多かったのですか?

ロンドン大学内のカフェコスタ
クラスメイトはイギリス人が多かったです。多いと行っても半分は占めていなくて、ヨーロッパやアメリカなどの人もいて国籍は色々いました。
–本当にネイティブかどうかは関係なく進むガチの世界ですね。

登校中の学生たちの様子
はい、ガチでした(笑)僕のようなネイティブじゃない人でもネイティブの人たちとガチで一緒のコースで学びますので。
クラスメイトの国籍の話ですと、僕のコースは分野が「教育と国際開発」でしたので、ウガンダ、ナイジェリアなどからの留学生も多かったです。
日本で留学生というと学生のイメージが強いと思いますが、イギリスの大学院では、僕のように社会人を経験してからの留学生が多くて、教育省関係の方とかもいました。
あと、ナイジェリア人で「教育大臣になる!」と宣言している人もいて、そういう環境がすごくおもしろかったです。
■大志さんが履修していた授業はどのようなものか?

大学院生を中心に開催されている勉強会「英国開発学勉強会(IDDP)」参加中の様子(出典:IDDPFacebookページ)
–大学院に通っているからこその出会いですね、うらやましいです!大志さんが取っていた4つの授業はどのようなものでしたか?
僕が取っていたのは
1..教育と国際開発「コンセプト、セオリー&イシュー」(開発の理論)
2.エデュケーション&デベロップメント in アジア
3.プランニング for エデュケーション&デベロップメント
4.EFA(エデュケーション for オール:万人のための教育)における学習と指導
でした。
–軽くでいいので、どのような事が学べるか教えていただけますか。

テムズ川で行われたのそばにロンドンマラソンを観戦に行った時の様子
はい、最初の「コンセプトセオリー&イシュー(以下、CTI)」は、国や地域が発展していく時のセオリーについて学びました。
簡単に言うと「理論やパターン」などです。そして、「セオリーを現場ではどのように使うか。」まで落とし込みます。ここで習ったセオリーを修士論文の中でもたくさん使ったので、僕にとってはすごくためになる授業でした。
同じタームで学んでいた「エデュケーション&デベロップメント in アジア」は、文字通り「アジアにおける教育と発展の関係」について学びました。
–事例研究のようなものでしょうか?
はい、そうですね。理論というよりは、実践的な内容でした。
例えば、「15年前に教育改革を行ったアジアの国で育った子どもたちが、大人になり、どのように成長していったか。」そして、「経済状況や国の状況はどのように変化していったか」などです。
このアジアの国には、東南アジアなどの途上国の他、台湾、韓国などの新興国も含まれます。この2つが秋のタームの10週間の授業です。
–なるほど。後の2つはどのようなものでしたか?
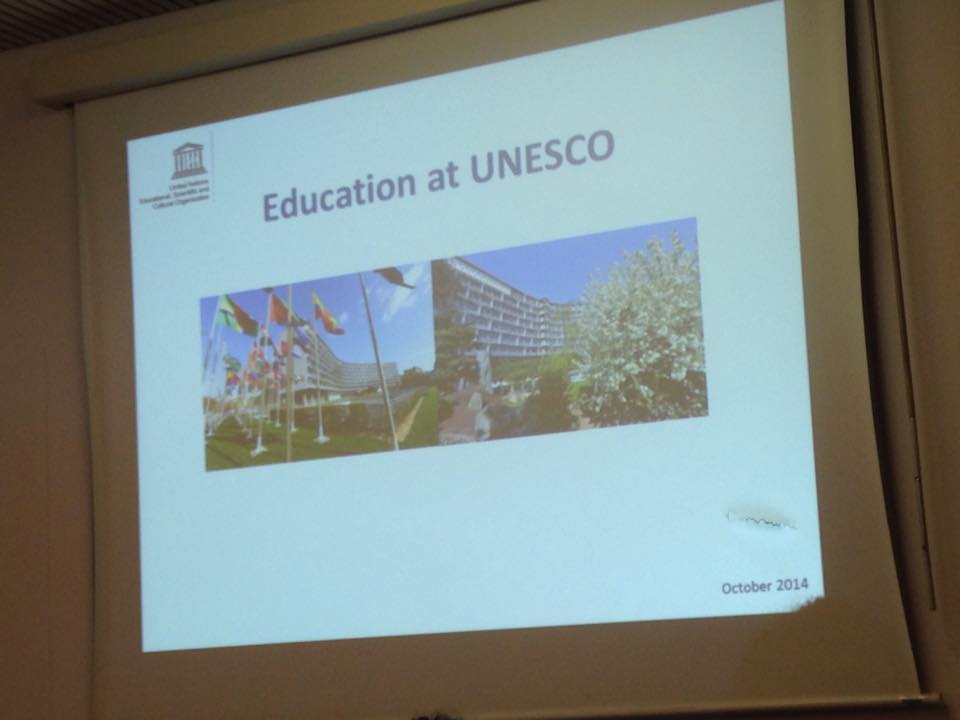
パリで行われた「Education at UNESCO」に参加された時の様子
「プランニング for エデュケーション&デベロップメント」は、「教育援助をする時のプランニング」について学ぶ授業でした。例えば、世界銀行やユネスコはこのようなフレームワークで行っているという型を学びます。
実際に援助活動に入る時は、「どのような目標や基準で行われているのか?」「その効果をどのようにして計るのか」そして「それをどう分析するか」などが大事になりますので、そういうのを教えてくれる授業でした。
–なるほど、実務に入る際に、これを知っているかどうかって大事そうですよね。なぜ、修士課程取得が就職に有利なのかがわかってきました。最後の授業はどのようなものでしたか?

IOEで開かれた”London Festival of Education 2015″の様子
最後の「エデュケーション for オール」は結構広い内容だったのですが、簡単に言うと「万人に教育を届けるために、現場で起きている話などを広くダイジェストのように学べる授業」でした。
例えば、「今回は、途上国で学校には行けるようになったけど、学校の質が低い問題が起きているので、先生のトレーニングの仕組みはどのようになっているのかを学ぶ」というものでした。
多分、一回づつの内容を深めていったら、1個の科目になるくらいの話を総合的に知れるものでした。
–どれも、国際協力や開発を学ぶ学生には魅力的な授業ですね。大志さん的には、どれが一番おもしろかったですか?
僕はやはり「CTI」が一番おもしろかったです!
先ほどもお話したように、僕が大学院に行きたいと思ったのは、「国際協力の分野で仕事をしたいな」と思ったからなので、CTIの授業は、今まで知らなかった「理論」や「今後に活かせる事」が学べたので、僕のやりたい事に一番ヒットしていました!
→【次ページ4/4】海外のレポートの大変さ、そしてフィールドワークから卒業へ



